児童手当(令和6年10月分(12月支給分)から一部制度改正)
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成を目的としています。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
児童手当制度改正のお知らせ(PDFファイル:135.9KB)
改正1:所得制限が撤廃されます
これまでは、児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給していました。今回の改正では、所得制限を撤廃し、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童を養育している人の所得にかかわらず児童手当が支給されます。
改正2:支給対象年齢が拡大します
これまでは、満15歳到達後の最初の3月31日(義務教育終了)までを支給対象年齢としていました。
今回の改正では、支給対象年齢を満18歳到達後の最初の3月31日までとなります。
改正3:第3子以降の手当額が増額します
これまでは、3歳以上小学生(または義務教育学校6年生)までの第3子以降の児童は、手当が第1子・第2子よりも加算され、月額15,000円でした。
今回の改正では、第3子以降は月額30,000円へと増額します。また、算定対象年齢が高校生年代から大学生年代まで拡大になったことに伴い、第3子としての加算が受けやすくなります。
詳しくは、支給月額をご確認ください。
改正4:支払月が年6回になります
これまでは年に3回の支払となっていましたが、令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、年に6回(偶数月)の支払いとなります。
詳しくは、支給月をご確認ください。
支給対象
春日部市に住民登録があり、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の日本国内に居住をしている児童を養育している父母などのうち、生計中心者が受給者となります。
- 養育している児童が住民票上別居となっている場合や、海外留学をしている場合は、必要書類を提出することで受給できることがあります
- 未成年後見人は、父母などに準ずる者として手当を受給することができます
- 児童の父母がともにいない場合は、養育者が受給できる場合があります
- 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します
- 父母が離婚協議中で住民票の異動を伴う別居をしているときは、対象児童と同居している人に支給する場合があります
- 父母が海外に居住している場合は、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します
| 支給対象児童 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 第1子、第2子 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで |
第1子、第2子 10,000円(第3子以降は30,000円) |
- 児童の数え方は、22歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます
- 上記の年齢を超えているこどもは、算定対象になりません。(例:25歳、10歳、5歳のこどもを養育している場合、10歳と5歳のこどもが、それぞれ第1子、第2子となります)
- 18歳に到達する日以後の最初の3月31日を迎えた児童は、支給対象外となります
年6回偶数月に、2ヶ月分をまとめて振り込みます。
振り込み予定日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、前日の平日になります。
なお、振込通知の発送は行われません。
| 振込予定日 | 対象 |
|---|---|
| 令和7年12月10日(水曜日) | 10月・11月分 |
| 令和8年2月10日(火曜日) | 12月・1月分 |
| 令和8年4月10日(金曜日) | 2月・3月分 |
| 令和8年6月10日(水曜日) | 4月・5月分 |
| 令和8年8月10日(月曜日) | 6月・7月分 |
| 令和8年10月9日(金曜日) | 8月・9月分 |
申請・変更手続き
申請に必要な書類
第1子を出生した場合・春日部市へ転入した場合
- 児童手当認定請求書(PDFファイル:256.9KB) 記入例(PDFファイル:321.8KB)
- 請求者本人名義の振込口座が確認できるもの(対象児童や配偶者名義の口座には振り込みできません)
- 請求者の本人確認書類
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・個人番号カード等)
- 官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(健康保険資格確認書・年金手帳等)
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号通知書等)
- 住民税の申告がお済みでない場合は申告してください(令和6年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村での申告となります)
- 請求者が下記に該当する人は、加入している健康保険の情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
加入している健康保険の情報が分かるものが必要な人
国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている場合
- 共済組合や職員団体の事務を行う人
- 国と民間企業の人事交流による派遣職員
- 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官など
- 行政執行法人の職員
- 国立大学法人の職員
- 日本郵政共済組合の組合員
地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされている場合
- 共済組合や職員団体の事務を行う人
- 公益的法人へ派遣されている地方公務員
- 特定地方独立行政法人の職員
注意事項
- 加入する年金の種類によって「被用者」「非被用者」と区別します。厚生年金・共済年金加入者は「被用者」、国民年金加入者や年金未加入者は「非被用者」になります
- 任意継続の場合は国民年金になります
- この他、マイナンバーを用いた情報連携による照会結果が申請内容と異なる場合など、加入年金の確認が困難な際は、別途加入している健康保険の情報が分かるものの提出を求めることがあります。詳しくはこども支援課まで問い合わせてください
第2子の出生などで支給対象児童が増加した場合
出生などで児童が3人以上となり、うち1人以上が算定児童(大学生年代)の場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:71.6KB)
- 今回の制度改正により、新たに必要となった様式です。
- 算定児童とは、18歳になって最初の3月31日を超えてから、22歳になって最初の3月31日を迎えるまでの児童のうち、受給資格者が経済的負担をしている者です。
- 上記の年齢を超えているこどもは、算定対象になりません。(例:25歳、10歳、5歳のこどもを養育している場合、10歳と5歳のこどもが、それぞれ第1子、第2子となります)
【例:23歳、21歳、10歳、1歳のこどもを養育している場合】
手当額
- 23歳:算定対象外
- 21歳:算定対象児童・第1子・手当支給なし
- 10歳:支給対象児童・第2子・月額10,000円
- 1歳:支給対象児童・第3子・月額30,000円
支給対象児童と住民票上別居の場合
- 児童手当別居監護申立書(PDFファイル:42.2KB)
- 支給対象児童の個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号通知書のいずれか(支給対象児童が春日部市に住民登録をしている場合は不要)
養育者が児童手当を受給する場合
監護・生計維持関係申立書 (PDFファイル: 226.1KB)
申請期間
子どもが生まれた人
出生日の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。
郵送での申請の場合、認定請求書が、こども支援課に到着した日が認定請求日となりますので、ご注意ください。
春日部市に転入した人
転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。
市民課での転入のお手続きを、先に済ませてからお越しください。
春日部市を転出した人
春日部市の転出予定日の翌日から15日以内、または同月内に転入先市区町村に申請してください。
春日部市を転出する場合、転出日をさかのぼった届け出をしたときは、返還金が生じることがあります。
公務員を退職した人
退職日の翌日から15日以内に、居住している市区町村へ申請してください。
その他の届け出
次のようなことがあった場合、届け出が必要です。届け出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還してもらう場合があります。
減額事由・消滅事由が発生したとき
事由
- 受給者または児童が、他の市区町村または国外へ転出したとき
- 児童が児童福祉施設などへ入所したとき
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 結婚などにより生計の中心者が変更になったとき
- 公務員採用となったとき
- 支給対象児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の監護・生計費の負担等がなくなったとき
届出書
住所、氏名に変更事由があったとき
事由
- 受給者または児童が市内転居をしたとき
- 受給者または児童が氏名を変更したとき
届出書
振込指定金融機関の支店名・店番号・口座番号に変更があったとき
受給者名義の口座のみ変更可能です。配偶者や児童名義の口座へ振り込むことはできません。
個人番号(12桁のマイナンバー)に変更が生じたとき
受給者およびその配偶者、対象児童の個人番号に変更が生じた場合、こども支援課 手当担当に連絡してください。
受給証明書について
令和6年10月分(12月振込分)より、口座振込通知書が発行されなくなります。受給状況に関する証明書が必要な場合は、受給証明書を発行いたしますので、春日部市役所こども支援課窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・個人番号カード等)
- 官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(健康保険資格確認書・年金手帳等)
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課 手当担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム


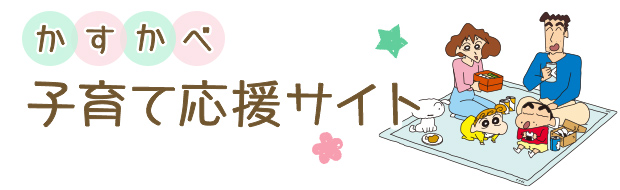

更新日:2024年10月07日