景観資源一覧
春日部市景観資源マップ
大落古利根川(公園橋周辺~藤塚橋周辺)
〔平成28年度登録〕
夏は水位が上がり、たっぷりと水をたたえた水面の様子が大変美しく、冬には水位の下がった川辺に生き物が集う様子が見られるなど、この区間の大落古利根川は、市街地にありながら季節ごとに異なる自然豊かな景観を間近で感じることのできる場所です。特に春には右岸も左岸も桜の花が咲き乱れ、大変華やかな時期を迎えます。また、遊歩道の除草や清掃、生垣の手入れなどが地域のボランティアの人たちによって行われているなど、来訪者にとって憩いの場所となっているだけでなく、周辺に住んでいる地域の人たちからも景観資源として大切にされています。


古利根公園橋
〔平成25年度登録〕
まちの中心を流れる大落古利根川に架かる全長79メートルの橋上公園です。「光と風」をテーマに、市の特産品である麦わら帽子をイメージした高さ14.5メートルのモニュメント、橋上ステージ、ブロンズ像6体などで構成するこの橋は、市政30周年(昭和59年)を記念して完成したものです。毎朝、地域住民がラジオ体操を行うなど、橋が市民生活の舞台になっていて、景観として印象的なものとなっています。


西金野井香取神社
〔平成25年度登録〕
西金野井香取神社は古くは「梶取明神」と呼ばれ、舟運に携わる人々から信仰を集めていました。本殿は「檜皮葺一間社流造 (ひわだぶきいっけんしゃながれづくり)」というヒノキ板の屋根が、ゆるやかな反りをもつことが特徴で、室町時代末期の建立と推定されており、県の有形文化財に指定されています。本香取神社には200メートル以上の参道があり、社殿の裏手側には江戸川沿いから来る裏参道の痕跡を見ることができます。社殿と参道、周囲の緑が一体となって一つの良好な景観を形成しています。


立野天満宮
〔平成25年度登録〕
創建は元久年間(1204年~1205年)と伝えられ、享保11年(1726年)に現在の地に鎮座したと伝えられています。現在の本殿は寛政元年(1789年)に再建されました。その造りは北野天満宮をかたどり、江戸時代後期の建築物としての特徴をよく表しています。基壇の上に神社本殿があって、その周りを木が取り囲んでいるのが、あたかもこの地域における昔からの水塚と屋敷林を思い起こさせます。


小淵山観音院 (こぶちざんかんのんいん)
〔平成25年度登録〕
小淵山観音院 (こぶちざんかんのんいん)は市内唯一の修験寺院で小淵山 正賢寺 (しょうけんじ)といいます。ご本尊は正観音 (しょうかんのん)で、いぼ・こぶ・あざ除けにご利益があるといわれ、境内には松尾 芭蕉 (まつおばしょう)の句碑もあります。元禄年間(1688年~1704年)に建てられた仁王門 (におうもん)は、二階部分に回廊が巡る三間一戸 (さんげんいっこ)形式の楼門で、市の有形文化財に指定されています。本堂は文政8年(1825年)に建てられたもので、仁王門、本堂、敷地内の樹木などが一体となって一つの良好な景観を形成しています。


庄和総合支所
〔平成25年度登録〕
公園の中に建設され、築山から流れるせせらぎの水を蓄えた池と、豊かな緑に溶け込んだ3階建ての庁舎です。大きな屋根とせず、小さな屋根の連続とすることで威圧感をやわらげ、木々の中でのスカイラインを考慮した環境にやさしいデザインとなっています。地域の暮らしに密着し、地域のシンボルにもなっています。

庄和総合公園
〔平成25年度登録〕
修景池の周りには高低のある木々が巧みに配置されています。花時計はボランティアによって入念に管理され、湿生植物コーナーはビオトープとなっており、散策する人々に親しまれ、景観資源として共有化されています。


ふじ通りの藤棚
〔平成25年度登録〕
春日部駅西口大沼線の春日部郵便局から春日部地方庁舎までのふじ通りは、歩道の両側約1キロメートルの間に、およそ200本のフジが植栽され、4月下旬から5月上旬に紫、白、ピンクの花を楽しませてくれます。毎年4月下旬に藤まつりが行われ、多くの見客が訪れます。市民のみならず近隣の地域の人からも親しまれています。


梅田 女體 (にょたい)神社
〔平成28年度登録〕
梅田 女體 (にょたい)神社は、地域の子どもが幼くして亡くなることが多かったことを憂い、子どもが健やかに育つようにと祈願し、国生みの神である伊邪那美尊 (いざなみのみこと)を祭ったのが起源で、延喜元年(901年)の創立以来、近隣の信仰を集めてきました。境内には大いちょうの他多数の巨木があり、梅田東地区の鎮守の森としての景観が今も残されています。また、社殿脇には富士信仰に基づいて築かれた富士塚があり、毎年7月1日には富士山の山開きの日から数えて1年以内に産まれた赤ちゃんの成長を願い、赤ちゃんを背負ってこの富士塚を登り、お祓いなどを受ける初山参りが行われ地域に親しまれています。


藤塚香取神社
〔平成28年度登録〕
藤塚香取神社は、古利根川左岸に形成された藤塚砂丘に建立され、境内には樹齢数百年の大けやきの他多数の巨木があり、春日部市の地形的な歴史景観を伝えているとともに鎮守の森としての景観も今なお残されています。広い境内は、例大祭などが行われるだけでなく、地域の人たちによる朝の体操なども行われ、南側に隣接する市の保育所をはじめとする周辺の地域の子どもたちに緑豊かな環境を提供しているなど、神社が地域の生活に溶け込んだ憩いの場となっています。


東八幡神社
〔平成28年度登録〕
東八幡神社は、国宝、京都男山の石清水八幡宮を勧請して、応神天皇を祭神とし、古くから氏子をはじめ、地域の多くの人々から厚い信仰を集め、「下 (しも)の八幡様」の愛称で親しまれてきました。天保6年(1835年)に建立された本殿や、社宝である本殿周囲の彫刻および樹齢約600年の大欅など、歴史を伝える貴重な文化財が残されています。また、秋の例大祭では、隔年ごとに大御輿 (みこし)が氏子町内を巡行し、町内の繁栄と発展をお祈りする習わしとなっています。


一の割公園
〔平成28年度登録〕
一の割公園は、公園内の除草や排水溝清掃などの環境美化活動が地域のボランティアの人たちによって行われています。公園内では、遊歩道の散策を楽しむ人の姿や、春には芝生の広場で桜のお花見を楽しむ人の姿が特に多く見られ、それ以外の季節でも毎朝地域の人たちが体操を行っているなど、公園が市民生活の舞台となっており、景観として印象的なものとなっています。


古隅田公園の竹林の遊歩道
〔平成28年度登録〕
西側を流れる古隅田川の氾濫を防ぐために築かれた堤防跡に、遊歩道が古隅田公園として整備されています。この区間の遊歩道沿いには竹林が続き、爽やかな木陰の空間を楽しむことのできる場所があり、景観資源として親しまれているほか、周辺には歴史を物語る史跡なども残されており、散策を楽しむ人の姿が多く見られます。


この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム
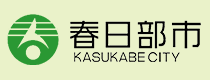

更新日:2021年12月15日