稲刈り後の水田管理について~早期耕耘の推奨~
稲刈り後の早期耕耘は様々なメリットがあります
稲刈り後の水田管理の1つである早期耕耘を推奨します。早期耕耘は土を柔らかくするだけでなく、雑草の分解や減少、病害虫の抑制にもつながります。下記内容を参照していただき、さらなる農業の充実にご活用ください。
1.稲わらの分解促進を行いワキを抑制しましょう
稲わらや刈り株が春先まで残ると、田んぼのワキ(硫化水素やメタンガス)の原因になります。稲わらや刈り株を早く分解させるには微生物の活動が活発な土の温度が15℃以上で、水田がまだいくらか湿り気のある真冬になる前に耕耘するのが有効です。
分解を促進することにより、田植え後の活着も良くなり、生育障害を軽減することができます。
また、土壌改良剤や堆肥を投入することで地力を回復させることにより、根の成長を促し高温障害対策にもつながります。
2.病害虫の居場所をなくし、発生を抑制しましょう
収穫後、再び刈り株から稲が生えるヒコバエはイネカメムシ等の病害虫の生息場所となり、再生株での縞葉枯病の発病も広く見られます。
放置すると病気のウイルスを獲得する可能性が高まり、翌年の被害が増加します。今年多発したイネカメムシはヒコバエを餌にして、成虫の越冬生存率を高めることにつながると考えられています。早期耕耘を心がけ、病害虫の越冬を防ぎましょう。
3.多年生の雑草の発生を防ぎましょう
クログワイやオモダカなどの水田雑草の塊茎は低温や乾燥に弱いため、秋冬期の耕耘を行うことで塊茎を地表面に露出させ死滅させることができます。
4.大雨時の稲わらの流出を防ぎましょう
早期に耕耘することで大風などの大雨時に稲わらが水田の端に溜まったり、水路や道路への流出、散乱を抑制できます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課 農業振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
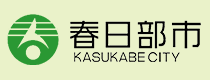

更新日:2024年12月10日