自立支援医療制度(精神通院医療)
精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費を含む)の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。自立支援医療制度(精神通院)受給者証を医療機関で提示することで制度を利用することができます。
対象者
精神疾患による通院医療(投薬を含む)を受けている方が対象です。 ただし、「重度かつ継続」に該当せず、一定以上の所得がある場合は、制度の対象外となります。
(注意)「重度かつ継続」の該当者とは、継続的な通院治療を受ける必要があり、相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかはその人の病状によって異なりますので、通院先の医療機関にお尋ねください。
制度の対象となる医療機関
精神通院医療の対象となる医療を実施する機関は、 埼玉県の指定自立支援医療機関のみです。
また、申請時に受診者が指定した病院・調剤薬局でのみ、この制度を利用できます。
申請手続きに必要なもの(新規申請や再認定申請の場合)
1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 申請書は窓口でお渡ししています。
- 再認定の手続きは毎年行う必要があります。
- 受診者が18歳未満の場合は保護者が記入してください。
- 指定医療機関の主治医が記載した日から3か月以内のものが必要です。
- 意見書の提出は2年に1回必要です。
- 意見書料金は自立支援医療費の支給対象にはなりません。
3. 健康保険資格情報が確認できる書類もしくは受診者本人のマイナ保険証(生活保護受給者を除く)
- 成年後見人を除く代理人が申請する場合、マイナ保険証はご利用いただけません。
- マイナポータルのログインには、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です。
- マイナ保険証をお持ちでない場合や健康保険資格情報が確認できる書類を持参される場合は以下1~3のいずれかで、資格取得日が記載されているものをご持参ください。
- カード表面に健康保険資格情報が記載されている従前の健康保険証はお使いいただけません。
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)の写し
- マイナポータルから資格情報の画面を印刷したもの(「資格取得日」と「被保険者氏名」を含む資格情報画面のスクリーンショットの写し、もしくは「端末に保存」をクリックして保存したPDFファイルの写し)
4. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等
- 受診者が18歳未満の場合は、本人と保護者のものが必要です。
5. 同意書(PDFファイル:263.1KB)(市で課税状況が確認できる場合のみ)
- 市町村民税が未申告の方は事前に申告が必要です。
6. 世帯(同一の健康保険等に加入している者全員)の所得状況を証明する書類等
- 春日部市で市町村民税が課税されている場合は、同意書の提出により省略することができます。
- 課税期間の翌1月1日に春日部市に住民登録がない場合は、保険が同一である世帯員全員の、課税(非課税)証明書、所得証明書、税額決定通知書等
7. 住民税非課税世帯については障害年金等の年金(注意1)や特別障害者手当等の手当(注意2)の分かる書類
- (注意1) 障害年金・遺族年金等の年金振込通知書や、課税年度の振込が記帳された通帳等
- (注意2) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当等を受給されている方は、振込額が記帳された通帳等
8. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証原本(再認定申請時)
9. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
10.生活保護受給者証(お持ちの方のみ)
11.本人および代理人の本人確認書類
- 本人による申請の場合 以下の 1 又は 2 が必要です。
1. 顔写真付き本人確認書類 1点 例:マイナ保険証、写真付きの障害者手帳、運転免許証など。
2. (1)官公署から発行された書類(顔写真なし)1点 例:資格確認書、各種年金証書、自立支援医療受給者証。
(2)氏名が分かる書類 1点 例:社員証、銀行の預金通帳やキャッシュカードなど。
計2点
- 代理人による申請の場合 以下の 3 及び 4 が必要です。
3. 自立支援医療受給者本人のもので、以下いずれかが必要です。
・官公署が発行する本人確認書類 例:マイナンバーカード
・戸籍謄本、登記事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
・家庭裁判所から送付される成年後見人制度等の審判書謄本等その資格が分かる書類
(成年後見人等の法定代理人の場合)
・任意の書式の委任状(任意代理人)
4. 代理人の本人確認書類(「・本人による申請の場合」に記載されている1又は 2と同様のもの)
初めて自立支援医療(精神通院)を申請する方は、意見書(診断書)を省略できる場合があります
初めて自立支援医療(精神通院)を申請する方で、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、上の「2.意見書(自立支援医療 精神通院用)」を省略できる場合があります。ただし、お持ちの手帳が手帳用診断書ではなく、障害年金証書の写し等の添付により交付された場合は意見書(診断書)等が必要です。また、申請時に入院中である方については、退院の見込みを確認する必要がありますので、意見書(診断書)等を提出していただくことがあります。
自己負担上限額や有効期間について
| 所得区分負担割合 | 負担割合 |
負担上限額「重度かつ継続」に該当する(注意1) |
負担上限額「重度かつ継続」に該当しない |
|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 負担なし | 0円 |
0円 |
|
所得区分 |
負担割合 |
負担上限額「重度かつ継続」に該当する(注意1) |
負担上限額「重度かつ継続」に該当しない |
|---|---|---|---|
|
80万9千円以下 (障害年金等を含む) |
1割 | 2,500円 | 2,500円 |
|
80万9千円超 (障害年金等を含む) |
1割 | 5,000円 | 5,000円 |
|
所得区分 |
負担割合 |
負担上限額「重度かつ継続」に該当する(注意1) |
負担上限額「重度かつ継続」に該当しない |
|---|---|---|---|
|
市町村民税額(所得割) 3万3千円未満 |
1割 | 5,000円 | 医療保険の自己負担上限額 |
|
市町村民税額(所得割) 3万3千円以上 23万5千円未満 |
1割 | 10,000円 | 医療保険の自己負担上限額 |
|
市町村民税額(所得割) 23万5千円以上 (注意2) |
1割 | 20,000円 |
自立支援医療 対象外 (負担割合3割) |
(注意1) 「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。
(注意2) 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過的特例措置となっておりますので、御了解くださいますよう、お願いします。令和9年4月1日からは対象外となりますので御注意ください。
- 「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を「同一世帯」とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
- 「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。
有効期間
- 有効期間は原則1年となります。
- 新規・再開申請の場合、窓口で申請書を受理した日が有効期間開始日となり、1年後の前月末日が有効期間の終了日となります。
- 再認定申請は、有効期間終了日の3か月前から手続きができます。
- 有効期間終了日および再認定に関するご案内はお送りしておりません。ご自身で受給者証の有効期間終了日をご確認のうえ、お早めにお手続ください。
申請手続きに必要なもの(変更申請や再交付申請の場合)
受給者証の一部を変更する場合
医療機関の変更や生活保護の開始・終了に伴う所得区分を変更する場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 申請書は窓口でお渡ししています。
住所、氏名、健康保険の情報等を変更する場合
2.自立支援医療受給者証等記載事項変更届(PDFファイル:114.6KB)
- 申請書は上記よりダウンロードまたは窓口にてお渡ししています。
変更申請に共通して必要な書類
3.自立支援医療(精神通院医療)受給者証
4.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等(受診者本人が18歳未満の場合は、本人と保護者のものが必要です。
申請内容により必要な書類
5.受診者本人の健康保険資格情報が確認できる書類(健康保険の情報を変更する場合)
- 「手続きに必要なもの(新規申請および再認定の場合)」の「3.受診者本人のマイナ保険証もしくは健康保険資格情報が確認できる書類(生活保護受給者を除く)」を参照してください。
6.生活保護の開始日や終了日がわかる書類(生活保護を受給されている場合のみ)
7.同意書(生活保護を終了される場合のみ)
受給者証を再交付する場合
1.自立支援医療受給者証再交付申請書(PDFファイル:40.8KB)
- 申請書は上記よりダウンロードまたは窓口でお渡ししています。
2.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等
3.本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカードをお持ちでない場合、顔写真付きの本人確認のできる書類が必要です。
受給者証が交付されるまでの目安の期間
1.新規申請・再認定申請の場合
- 受給者証が交付されるまでに、約3か月ほどかかります。
2.変更申請の場合
- 受給者証の記載内容の変更手続きは、原則として即日で行います。
3.受給者証を再交付する場合
- 受給者証が再交付されるまでに、約1か月ほどかかります。
県外に転出される場合やお亡くなりになった場合
受診者が県外に転出される場合
受診者が県外に転出される場合、障がい者支援課の窓口で転帰登録をしていただく必要があります。以下の書類を障がい者支援課にお持ちください。
- 転帰・中断処理票(障がい者支援課の窓口にあります)
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証
受診者がお亡くなりになった場合
有効期間内に受診者本人が亡くなられた場合、中断登録および自立支援医療(精神通院)受給者証を返還する手続きが必要です。なお、有効期限が切れた自立支援医療受給者証は、転帰・中断処理票の記入は必要ありませんので、受給者証を障がい者支援課へお持ちいただくか、ご自身で処分してください。
- 転帰・中断処理票(障がい者支援課の窓口にあります)
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証
自立支援医療(精神通院)受給者証と精神障害者保健福祉手帳の両方をお持ちの場合
転帰・中断登録は、自立支援医療(精神通院)受給者証と精神障害者保健福祉手帳両方を同時に処理することができます。転帰・中断登録を行う際に、精神障害者保健福祉手帳もお持ちの方はお知らせください。
郵送でのお手続きをご希望される場合
遠方にお住まいのご家族が申請手続きをされる場合など、郵送での申請をご希望される方は、障がい者支援課までお問い合わせください。
書類のダウンロード
1.申請に関する書類
意見書(自立支援医療 精神通院用)
同意書
自立支援医療受給者証記載事項変更届
自立支援医療受給者証等記載事項変更届 (PDFファイル: 72.0KB)
自立支援医療受給者証再交付申請書
自立支援医療受給者証再交付申請書(精神通院医療) (PDFファイル: 40.8KB)
2.手続きに関するご案内
自立支援医療(精神通院)新規申請手続きのご案内
自立支援医療(精神通院)新規申請手続きのご案内 (PDFファイル: 66.7KB)
自立支援医療(精神通院)再認定申請手続きのご案内
自立支援医療(精神通院)再認定申請手続きのご案内 (PDFファイル: 66.3KB)
自立支援医療(精神通院)変更・再交付申請手続きのご案内
自立支援医療(精神通院)変更・再交付申請手続きのご案内 (PDFファイル: 61.5KB)
お問い合わせ
障がい者支援課 障がい者支援担当
- 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
- 電話:048-736-1131
- ファックス:048-733-0220
庄和総合支所 福祉・健康保険担当
- 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
- 電話:048-746-9702
- ファックス:048-746-4797
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
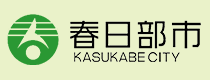

更新日:2025年12月02日