障害児通所支援
障害児通所支援とは、心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育、訓練等を行う支援です。
対象となる児童
以下の条件を満たす18歳未満の児童
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)をお持ちの方
- 特別児童扶養手当の受給対象となる方
- 医師の診断書や意見書、発達検査の結果等で療育、訓練の必要性があると判断された方
- 難病のある方(指定難病医療受給者証の交付を受けている、又は当該対象疾病の診断のある)等
医師の診断書、意見書には指定の様式はありませんが、診断名、又は療育が必要となる旨の記載されていることが必要です。
サービス更新時には医師の診断書等を新たに取得し、提出していただきます。(診断書で利用対象者の確認を行った方のうち、次年度に小・中・高校に入学する方のみ)
サービス種類
| サービスの名称 | サービスの内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援、又はこれに併せて治療を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して、発達支援を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 就学児を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 支援員が保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援や、その他必要な支援を行います。 |
| 障害児相談支援 | 障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容等について「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を作成し、その後継続的な支援を行います。 |
利用者負担について
利用者負担上限月額
原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
利用者負担額は、世帯の所得に応じて1か月当たりの上限額が決められており、サービス事業者に支払います。世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳の世帯全員です。
なお、障害児相談支援に係る費用については、利用者負担はありません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯のうち市民税所得割額が28万円未満 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
就学前児童発達支援の無償化について
満3歳になった翌年度の4月1日から小学校就学前までは、利用者負担上限月額に関わらず、無償となります。利用者負担外の費用(食費等の実費で負担するもの等)はお支払いください。
利用者負担上限額の管理
- 兄弟姉妹等での利用、または複数の障害児通所支援事業所を利用する場合は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入し障がい者支援課または庄和総合支所福祉・健康保険担当へ提出してください。
- 利用者負担上限月額が0円の方及び無償化対象期間の対象児は、上限月額の管理を依頼する必要はありません。
未就学児の多子軽減措置について
- 市民税課税世帯のうち、生計を同じくする兄または姉がいる(市民税所得割の合算額が77,101円以上の世帯は、保育園、幼稚園、認定こども園、児童発達支援等に通う兄または姉がいる)世帯に対し、第2子以降の障害児通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援)の利用者負担額を軽減する制度があります。
- 無償化対象期間の対象児は、利用者負担かかかりません。
- 利用者負担以外の費用(食費等の実費で負担するもの等)はお支払いください。
高額障害福祉サービス費
- 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合等に、利用者負担の軽減があります。
詳細については障がい者支援課、庄和総合支所福祉・健康保険担当にお問い合わせください。
サービスの利用までの流れ
(1)サービスの利用相談
市(障がい者支援課又は庄和総合支所福祉・健康保険担当)の窓口に相談します。
(2)申請
市(障がい者支援課又は庄和総合支所福祉・健康保険担当)の窓口で申請します。
サービスを利用する必要性の分かるもの(障害者手帳、診断書等)を持参してください。
(3)面談・アセスメント
申請者等のニーズについて、担当ケースワーカーによる、聞き取り(アセスメント)を行います。
事前に障がい者支援課又は庄和総合支所福祉・健康保険担当にお電話等で予約をお願いします。
(4)支援会議 令和7年10月1日~開始
面談内容を勘案し、今後の援助方針等を策定するため支援会議を実施します。
(5)計画案・セルフプランの提出
サービス等利用計画案を作成可能な相談支援事業所を決定し、作成を依頼してください。
なお、希望される場合はセルフプランの提出が可能です。
計画相談、セルフプランについての詳細は、計画相談支援・障害児相談支援でご確認ください。
(6)支給決定
サービスの支給決定後、支給決定通知書及び受給者証を送付します。
(7)計画の提出(セルフプランの方は不要)
指定特定相談支援事業所に計画案の作成依頼した場合、サービス担当者会議を開き計画を完成させます。利用者の同意を得た後に、利用者及びサービス提供事業所に交付し、その写しを市へ提出します。
(8)利用開始
利用開始日は原則、月の初日からになります。
詳細は下表のとおりです。
| 申請日 | 利用開始日 |
|---|---|
| 1日~15日まで | 翌月1日~ |
| 16日~月末まで | 翌々月1日~ |
(9)モニタリング
指定特定相談支援事業所は、定められた月ごとに利用者の居宅等を訪問し、適切な助言等を行います。
セルフプランを利用している方で、サービスを更新する場合、自己評価シートを作成していただきます。
申請様式
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
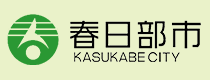

更新日:2026年02月19日