令和7年度春日部市で受けられる小児の定期予防接種
予防接種法に基づき、実施医療機関で通年実施(個別接種)します。
厚生労働省ホームページ「予防接種情報」(外部サイト)でも詳しい情報をお知らせしています。
令和8年3月1日(日曜日)から7日(土曜日)は、「子ども予防接種週間」です。
予防接種情報提供サービス「かすかべっこ予防接種ナビ」を利用してください
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)(DPT-IPV-Hib)
- 対象は市内に住民登録のある人です。対象年齢は、各予防接種によって異なります
- 対象年齢になったら、体調の良いときに早めに接種しましょう
- 接種費用は無料(公費負担)です
- 必ず、対象年齢内、決められた接種間隔、接種回数で接種しましょう。対象年齢以外で接種した場合、規定の接種回数を超えて接種した場合、接種間隔が規定より短い場合は有料です
- 予防接種を受ける際に必要な各予防接種の予診票などは、生後6週までに個別に郵送します。転入や紛失などで予診票がない場合は、健康課 予防担当へお問い合わせください
予防接種の対象年齢の考え方
予防接種では「年齢計算ニ関スル法律」に基づき、誕生日の前日に年を取ると考えます。各予防接種は対象年齢(月齢)になる日の前日から無料で受けられます。ただし、麻しん(はしか)・風しん混合2期は、保育所・幼稚園などの年長児の1年間(4月1日~翌年3月31日)が無料で受けられる期間です。
例:対象年齢が「生後2カ月~1歳」の場合
誕生日が令和7年4月1日の人は、令和7年6月1日の前日(5月31日)~令和8年4月1日の前日(3月31日)が無料で接種を受けられる期間です。
他の予防接種との間隔
生ワクチン(注射)接種後、異なる生ワクチン(注射)を接種する場合は、接種の翌日から27日以上の間隔を空けてださい。生ワクチン(注射)から生ワクチン(注射)以外の接種間隔の制限はありません。接種方法は、実施医療機関を確認してください。
| 定期接種 | ロタウイルス(令和2年8月1日以降に生まれた人)、BCG、麻しん・風しん混合(MR)、水痘 |
|---|---|
| 任意接種 | ロタウイルス(令和2年7月31日以前に生まれた人)、おたふくかぜなど |
ロタウイルス:経口接種
| 定期接種 |
B型肝炎、小児用肺炎球菌、5種混合、日本脳炎、2種混合、子宮頸(けい)がん |
|---|---|
| 任意接種 | インフルエンザなど |
任意接種:予防接種法に基づかない接種で有料
予防接種を受けに行く前に
- 子どもの体調が良いときに受けましょう
- 当日受ける予防接種の「予防接種と子どもの健康」を読んで、必要性、効果および副反応などを理解した上で受けましょう
- 母子健康手帳を必ず持って行きましょう(実施医療機関で接種間隔などを確認します)
- 予診票は接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入するようにしましょう
- 予防接種を受ける子どもの日頃の健康状態をよく知っている保護者が連れて行きましょう
予防接種を受けることができない人
- 明らかに発熱(通常37.5度以上)している
- 急性疾患にかかっていることが明らか
- 当日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分でアナフィラキシー反応を起こしたことがある
- その他、医師に不適当な状態と判断された
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり、定期予防接種が受けられなかった人
接種不適当要因解消後、2年間は定期予防接種が受けられます。該当者は、健康課 予防担当へお問い合わせください。
予防接種を受ける際に注意を要する人
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている
- 予防接種で、接種後2日以内に発熱がみられた、および発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある
- 過去に免疫不全の診断をされている子ども、および近親者に先天性免疫不全症の人がいる
- 卵の成分、抗生物質などでアレルギーがあると言われたことがある
- B型肝炎予防接種の場合は、ラテックス過敏症(注意1)がある
- BCG予防接種の場合は、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いがある
- ロタウイルスの予防接種の場合は、活動性胃腸疾患や下痢などの胃腸障害がある
(注意1)ラテックス過敏症:天然ゴムの製品に対する即時性の過敏症
予防接種を受けた後の一般的注意事項
- 予防接種を受けた後30分程度は、医療機関で子どもの様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう
- 接種当日は、激しい運動は避けましょう
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう
副反応が起こった場合の対応
予防接種を受けた後、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。子どもの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人 医薬品医療機器総合機構へ副反応の報告が行われます。
ワクチンの種類によっては、まれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
予防接種による健康被害救済制度
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます(国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます)。
詳細は厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。
保護者が子どもの予防接種に同伴できない場合
予防接種を受ける際は、原則、保護者の同伴が必要です。やむを得ず、親族などが同伴する場合は、保護者が作成した委任状が必要になります。詳しくは、保護者が子どもの予防接種に同伴できない場合は委任状の提出をご覧ください(委任状 様式をダウンロードできます)。
予防接種を受ける時の持ち物
- 母子健康手帳(必ずお持ちください。接種間隔などを確認します)
- マイナ保険証またはそのかわりになるもの
- 予診票
- 委任状(保護者が同伴できない場合)
紛失などで、母子健康手帳や予診票のない人は、健康課 予防担当へお問い合わせください。
予防接種を受ける場合は、実施医療機関で予約をして受けましょう。
埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受ける場合は、市内の実施医療機関と同じように接種できます。接種協力医療機関で実施の有無を確認の上、接種を受けてください。
埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿(一般社団法人 埼玉県医師会のサイト)(外部サイト)
市外での接種を希望する人で、上記の医療機関以外で接種する人は、予防接種助成金制度を利用してください。
春日部市予防接種等助成金制度
市外の医療機関などで接種を受ける人に、接種費用の一部を助成(上限あり)する制度です。
接種を受ける前に申請が必要です。接種前に申請していない場合、助成金の交付はできませんのでご注意ください。
対象者
市外(国内に限る)の医療機関等(埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ医療機関等を除く)で接種を受ける、次に該当する市民
- 里帰りなどで他市町村の医療機関で接種を受ける人
- 長期入院している人
- かかりつけ医が他市町村にある人
- 施設に入所している人
申請方法
接種の2週間以上前に必要な手続き
- 「春日部市予防接種等依頼書(A類疾病定期接種・再接種・任意接種・風しん抗体検査)交付申請書(保護者が記入)」に必要事項を記入し、下記申請場所へ提出してください。様式は次からダウンロード、または、健康課 予防担当へ連絡してください
- 「春日部市予防接種等依頼書(A類疾病定期接種・再接種・任意接種・風しん抗体検査)交付申請書」を提出後、2週間くらいで、申請書に記入された住所に「春日部市予防接種等依頼書」が郵送されます
- 接種を受ける際は、市から郵送された「春日部市予防接種等依頼書」と、「春日部市予防接種予診票(必要事項を記入)」を接種医療機関に提出の上、接種を受けてください
接種後、早めに必要な手続き
接種後、次のものを持って、早めに「春日部市予防接種等助成金交付申請書兼請求書」を下記申請場所へ提出してください。様式は次からダウンロード、または、健康課 予防担当へ連絡してください。
- 春日部市予防接種等助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:102.5KB)
- 記入例(PDFファイル:222.9KB)
- 実施済みの予診票(原本または写し)、母子健康手帳の写しまたは予防接種の記録
- 領収書および明細書(原本または写し)
- 印鑑(朱肉を必要とする印鑑)
- 振り込みを希望する金融機関の口座番号など(申請者(保護者)名義のもの)が分かるもの(申請者名義の口座がないなどの理由で、申請者名義以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状(申請者自署のもの)が必要になります。委任状(PDFファイル:66.9KB)
予防接種実施後、なるべく早めに申請してください。接種してから1年を過ぎると助成対象外となります。
申請場所
市役所本庁舎2階 健康課 予防担当(月曜日~金曜日(閉庁日を除く))
電話:048-736-1199(健康課直通)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
子どもの予防接種の接種状況、接種したい予防接種を選択すると、システムが自動でスケジュールを作成し、予防接種を受ける日をメールで知らせてくれるサービスです。利用には、子どものニックネーム、生年月日、郵便番号、メールアドレスの登録が必要です。12カ国語に対応しています。
接種方法が標準的な接種間隔です。なるべく標準的な接種間隔を守って接種しましょう。標準的な接種間隔を過ぎた場合でも、対象年齢内なら無料で接種できます。接種間隔が規定より短い場合は有料になります。
対象年齢
- 1価ワクチン(ロタリックス):生後6週0日(標準的接種開始年齢は2カ月)~生後24週0日
- 5価ワクチン(ロタテック):生後6週0日(標準的接種開始年齢は2カ月)~生後32週0日
週数の数え方
- 生後6週0日:生まれてから6回目の、生まれた日と同じ曜日
- 生後14週6日:生まれてから15回目の、生まれた日と同じ曜日の1日前
- 生後24週0日:生まれてから24回目の、生まれた日と同じ曜日
- 生後32週0日:生まれてから32回目の、生まれた日と同じ曜日
接種方法
使用するワクチンにより接種回数が異なります(経口投与)。
- 1価ワクチン(ロタリックス):27日以上の間隔をあけて2回接種
- 5価ワクチン(ロタテック):27日以上の間隔をあけて3回接種
注意事項
- ロタウイルスワクチン2種類ありますが、同様の効果があります。実施医療機関にあるワクチンを接種してください
- 腸重積症の起こりにくい早めの時期に接種を受けましょう。1回目の接種は、生後14週6日までに受けましょう
- 2回目、3回目は、1回目と同じワクチンを接種してください
- 接種後は、腸重積症に気をつけましょう。ワクチン接種後、1~2週間くらいの間は、かかりやすくなると報告されています
接種方法が標準的な接種間隔です。なるべく標準的な接種間隔を守って接種しましょう。標準的な接種間隔を過ぎた場合でも、対象年齢内なら無料で接種できます。接種間隔が規定より短い場合は有料になります。
対象年齢
生後2カ月~9カ月になる日の前日(1歳の誕生日の前日までは無料で受けられます)
接種方法
3回接種(皮下注射)
- 1回目接種:生後2カ月から接種
- 2回目接種:1回目接種から27日以上の間隔を空けて接種(1回目接種から4週間後の同じ曜日以降接種可)
- 3回目接種:2回目接種後、1回目接種から139日以上の間隔を空けて接種(1回目接種から20週間後の同じ曜日以降接種可)
注意事項
- B型肝炎ワクチンは2種類ありますが、実施医療機関にあるワクチンを接種してください(ラテックス(天然ゴム)過敏症(注意1)の人に注意が必要なワクチンがありますので、近親者に過敏症の人がいる場合は実施医療機関に相談の上、接種を受けてください)
- 母子感染予防のためにB型肝炎予防接種を受けた人は、接種する必要はありません
(注意1)ラテックス(天然ゴム)過敏症:天然ゴムの製品に対する即時性の過敏症です。ラテックス製の手袋使用時にアレルギー反応がみられた場合に疑います。また、ラテックスと交叉反応のある果物など(バナナ、栗、キウイフルーツ、アボカド、メロンなど)にアレルギーがある場合は、接種医に相談してください。
生後2カ月~7カ月になる日の前日までに接種を始めるのが「標準的接種スケジュール」です。なるべく接種間隔を守って接種しましょう。標準的な接種間隔を過ぎた場合でも、対象年齢内、規定の接種回数なら無料で接種できます。接種間隔が規定より短い場合は有料になります。早めに受け始めましょう。
対象年齢
生後2カ月~5歳の誕生日の前日
接種方法
皮下注射・筋肉内注射
接種回数
受け始める年齢(月齢)によって、接種する回数が異なります
| 接種開始年齢 | 接種回数 | 接種間隔など |
|---|---|---|
| 生後2カ月~7カ月になる日の前日 (標準的接種スケジュール) |
4回 |
|
| 生後7カ月~1歳の誕生日の前日 | 3回 |
|
| 1歳~2歳の誕生日の前日 | 2回 | 60日以上の間隔を空けて2回接種(5歳の誕生日の前日まで無料) |
| 2歳~5歳の誕生日の前日 | 1回 | 5歳の誕生日の前日までは無料で受けられます |
接種方法が標準的な接種間隔です。なるべく標準的な接種間隔を守って接種しましょう(標準的な接種間隔を過ぎた場合でも、対象年齢内なら無料で接種できます。接種間隔が規定より短い場合は有料になります)。
5種混合は、ヒブと4種混合の混合ワクチンです。
5種混合を接種した場合、ヒブと4種混合の接種は必要ありません。
対象年齢
生後2カ月~7歳6カ月になる日の前日
接種方法
全4回接種(皮下注射・筋肉内注射)
- 1期:20日~56日の間隔を空けて3回接種
- 追加:1期接種(3回)から、6カ月~18カ月の間隔を空けて1回接種(1期接種(3回)から、6カ月以上空ければ接種可)
生後2カ月~7カ月になる日の前日までに接種を始めるのが「標準的接種スケジュール」です。なるべく接種間隔を守って接種しましょう。標準的な接種間隔を過ぎた場合でも、対象年齢内、規定の接種回数なら無料で接種できます。接種間隔が規定より短い場合は有料になります。
ヒブと4種混合が未接種の場合は、5種混合での接種となります。
ヒブと4種混合の接種回数が同一の場合は、5種混合への切り替えが可能です。
対象年齢
生後2カ月~5歳の誕生日の前日
接種方法
皮下注射
接種回数
受け始める年齢(月齢)によって、接種する回数が異なります。早めに受け始めましょう。
| 接種開始年齢 | 接種回数 | 接種間隔など |
|---|---|---|
| 生後2カ月~7カ月になる日の前日 (標準的接種スケジュール) |
4回 |
|
| 生後7カ月~1歳の誕生日の前日 | 3回 |
|
| 1歳~5歳の誕生日の前日 | 1回 | 5歳の誕生日の前日までは無料で受けられます |
4種混合ワクチンの接種が完了していない方
令和6年4月1日から5種混合ワクチンが定期接種化したことに伴い、4種混合ワクチンの製造販売が終了しました。
4種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始した方で、4種混合ワクチンの接種が完了していない場合、ヒブワクチンの接種回数にかかわらず、5種混合ワクチンを用いて接種を完了することも可能です。
(注意)接種を希望する場合には、5種混合の予診票が必要になります。4種混合の予診票と交換いたしますので、事前に健康課へお問い合わせください。市内の医療機関で接種を希望する場合には、病院にも予診票が置いてあります。
ヒブワクチンが完了している方は、4種混合ワクチンの代わりに、3種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンを接種する方法もありますが、3種混合ワクチンは、全国的に需要が高まり、限定出荷となっています。接種を希望しても、入手困難ですぐに接種できず、長期お待ちいただく場合があります。
(例)ヒブと4種混合を初回接種として各3回接種→5種混合を追加接種として1回接種
(例)ヒブ4回、4種混合3回→5種混合1回または3種混合と不活化ポリオを各1回
対象年齢
生後2カ月~7歳6カ月になる日の前日
接種方法
全4回接種(皮下注射)
- 1期:20日~56日の間隔を空けて3回接種
- 追加:1期接種(3回)から、1年~1年6カ月の間隔を空けて1回接種(1期接種(3回)から、6カ月以上空ければ接種可)
4種混合または、5種混合を接種する人は不活化ポリオを接種する必要はありません。
これから予防接種を始める人は、原則5種混合を接種します。
単独の不活化ポリオのみが接種途中の人は、残りの回数も単独の不活化ポリオを接種してください。
対象年齢
生後2カ月~7歳6カ月になる日の前日
接種方法
全4回接種(皮下注射)
- 1期:20日~56日の間隔を空けて3回接種
- 追加:1期接種(3回)から、1年~1年6カ月の間隔を空けて1回接種(1期接種(3回)から、6カ月以上空ければ接種可)
対象年齢
生後5カ月~8カ月になる日の前日(1歳の誕生日の前日までは無料で受けられます)
接種方法
1回接種(経皮注射)
対象年齢
- 第1期:1歳~2歳の誕生日の前日
- 第2期:保育所・幼稚園などの年長児(平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ)
接種方法
各1回接種(皮下注射)
麻しん及び風しんの定期予防接種期間の延長について
厚生労働省は、ワクチンの供給不足により、乾燥弱毒製麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の定期接種期間を2年間延長する方針を決定しました。
対象者
第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
(注意)第1期、第2期いずれもワクチン供給不足により接種できなかった方
(注意)対象者用の予診票をお渡ししますので、必ず事前に健康課へお問い合わせください。
接種方法が標準的な接種間隔です。なるべく標準的な接種間隔を守って接種しましょう。標準的な接種間隔を過ぎた場合でも、対象年齢内なら無料で接種できます。接種間隔が規定より短い場合は有料になります。
対象年齢
1歳~3歳の誕生日の前日
接種方法
全2回接種(皮下注射)
6カ月~12カ月の間隔を空けて2回接種(3カ月以上空ければ接種可)
麻しん(はしか)・風しん混合予防接種(第1期)が終了して、27日以上たったら、早めに接種しましょう。1回目の接種は、1歳~1歳3カ月に受けることが望ましいとされています。
接種方法が標準的な接種間隔です。なるべく標準的な接種間隔を守って接種しましょう。標準的な接種間隔を過ぎた場合でも、対象年齢内なら無料で接種できます。接種間隔が規定より短い場合は有料になります。
対象年齢
- 1期:3歳~7歳6カ月になる日の前日
- 2期:9歳~13歳の誕生日の前日
希望者は生後6カ月から無料で受けられます。
接種方法
全4回接種(皮下注射)
- 1期:6日~28日の間隔を空けて2回接種
- 追加:1期接種(2回)から、おおむね1年後に1回接種(1期接種(2回)から、6カ月以上空ければ接種可)
- 2期:1回接種(9歳になったら受けましょう)
特例措置対象者
特例措置対象者(下記の生年月日の人)は、それぞれの対象年齢内に1期・追加・2期の両方を接種できます。
平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの人
20歳の誕生日の前日まで受けられます。
対象年齢
11歳~13歳の誕生日の前日
接種方法
1回接種(皮下注射)
乳幼児期に受けた4種混合予防接種の追加接種です。
小学校6年生相当になる女子には、対象となる年度の初めに予診票を送付します。
接種に当たっては、有効性とリスクを理解した上で受けてください。
詳しくは、「HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの接種について」をご覧ください。
転入、紛失などで予診票のない人は、母子健康手帳で接種歴を確認のうえ、健康課予防担当の窓口にてお渡しします。母子健康手帳、本人確認書類を必ずお持ちください。
対象者
・通常の定期接種対象者
小学校6年生~高校1年生相当の女子(平成21年4月2日~平成26年4月1日生まれ)
・キャッチアップ接種 経過措置対象者
平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性のうち
令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に1回以上HPVワクチンを接種した方
副反応
ワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、恐怖、興奮をきっかけとした失神などがあげられます。詳しくは、厚生労働省ホームページHPVワクチンQ&Aをご覧ください。
注意事項
- 接種後に、血管迷走神経反射(針を刺すことによる痛みやストレスなどで起こる神経反射)による失神を起こすことがありますので、すぐに帰宅せず、少なくとも30分間は安静にしてください
- 接種を受けても全てのHPVの感染を予防できるわけではありません。20歳になったら定期的に子宮頸がん検診を受けましょう
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 予防担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
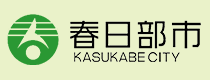

更新日:2026年01月21日