限度区分申請(旧限度額適用・標準負担額減額認定証)
主に入院など、医療費が高額になる時に、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめるための申請です。
令和6年12月2日以降、現行の保険証が廃止されたことに合わせて、限度額適用認定証等の新規発行は終了しました。
令和6年12月2日以降は限度区分を記載した資格確認書を発行しています。
マイナ保険証をご利用の方は、申請不要です。
ひと月の自己負担限度額について
| 所得区分 | 外来(個人ごと)の自己負担限度額 | 入院+外来(世帯合算)の自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上の人) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント(多数回該当140,100円) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント(多数回該当140,100円) |
|
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上690万円未満の人) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント(多数回該当93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント(多数回該当93,000円) |
|
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上380万円未満の人) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント(多数回該当44,400円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント(多数回該当44,400円) |
|
一般2 (2割負担者) |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (多数回該当44,400円) |
| 一般1 |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (多数回該当44,400円) |
|
区分2 (世帯全員が住民税非課税である人) |
8,000円 | 24,600円 |
|
区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円 (年金所得は控除額80.67万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)である人) |
8,000円 | 15,000円 |
- 多数回該当…過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降に該当するひと月の上限額となります。
- 差額ベッド代、リネン代などは医療保険の適用外のため、高額療養費の対象に含まれません。
区分1・2、現役並み所得者1・2に該当する方について
限度区分申請
入院等で高額な医療費がかかる場合は、申請いただくことで、資格確認書に限度区分を併記することができます。
限度区分を併記した資格確認書を医療機関等に提示することで、同一の医療機関等でお支払いいただく医療費が、自己負担限度額までとなります。
申請の対象となるか分からない場合は、後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口で限度額情報の提供に同意することで、申請手続きなく、自己負担限度額を超えての支払いが免除されます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細
長期入院該当について
限度区分2の方で、次の要件を満たすと食事負担額がさらに軽減される制度です。
- 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合
(注意1)過去1年間で区分の変動がある人は、区分2に該当する期間の入院日数をカウントします。
(注意2) マイナ保険証を利用し、自己負担限度額を超える支払いが免除されている人も、長期入院の要件に該当した際には届出が必要です。
申請窓口
- 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
- 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
必要な物
- 資格確認書
長期入院に該当し、入院日数の届け出をする人は、以下のものが必要です。
- 被保険者の入院期間の分かるもの(医療機関の領収書など)
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
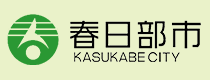

更新日:2026年02月10日