住宅火災に関する注意喚起について
令和7年中の火災発生件数82件(令和7年1月1日から12月31日)
令和7年中は1か月の間に約7件の火災が発生したことになります。
火災はちょっとした不注意や一瞬の油断から発生し、貴重な財産や大切な思い出を失うことになります。家庭で火災予防対策を徹底し、火災を起こさないよう十分注意してください。
(注意)令和6年中の火災発生件数は55件でした。
住宅防火 いのちを守る10のポイント
4つの習慣
- 寝たばこは絶対にしない、させない
- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
- こんろを使うときは火のそばを離れない
- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く


6つの対策
- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
- 火災を早期発見するために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保しておく
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う


事例から学ぶ火災予防
-
たばこの吸い殻は水につけて消し、灰皿の吸い殻は小まめに捨てる
灰皿に吸い殻がたまってくると、もみ消したつもりがきちんと消えていないことがあります。確実に火を消すために、水につけて消す習慣を心掛けましょう。
- 電気製品や火を使用する器具は、正しい使用方法をきちんと守る
使い勝手がいいから、これくらい大丈夫だろう等といった理由で、誤った使用方法をしていると、思いがけず火災になることがあります。それぞれの取扱説明書で禁止されている行為は行わないようにしましょう。
- 電気コードの取り扱いに注意する
電気コードは束ねたまま使用していると、熱がたまり、発火することがあります。また、電気コードの被覆がはがれているものや、断線しているものも発火し火災の原因になることがあります。
- 環境美化を心掛け、放火されにくい環境をつくる
過去5年間の出火原因別でも、放火が原因と思われる火災は一定数発生しています。敷地内の見えやすい場所に可燃物や灯油のポリタンク等を置かないようにしましょう。
もしも火災が発生してしまったときは
- 落ち着いて119番通報をする
119番通報の遅れが、そのまま消防隊の到着の遅れになります。周囲の人が気付くくらいになってからでは、被害が大きくなってしまいます。
通報する際は、住所(発生場所)、名前、何が燃えているか等を伝えてください。
- 周囲に火災を知らせる
家族や近所の人に大きな声で火災を知らせましょう。
- 初期消火を試みる
119番通報をしたあと、可能であれば初期消火を試みてください。
- 無理をせず避難を優先する
煙が発生して息苦しさがあったり、火が天井まで燃え移ってしまった場合は、迷わずいのちを守る行動を優先してください。
大切な命と財産を守るため、日頃から火災予防に心がけるとともに、万が一火災が発生した場合の対策も講じましょう。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532
ファックス:048-738-3200
お問い合わせフォーム
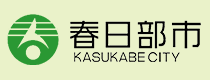

更新日:2026年01月30日