感染症に関する情報
最新の感染症流行情報は、埼玉県ホームページ感染症情報センター「最新の感染症流行情報」(外部サイト)をご覧ください。
目次
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染することによって引き起こされる病気です。
感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。また、ウイルスが付いたものに触った後、手を洗わずに、目や鼻、口を触ることにより感染することもあります。
症状
発熱、呼吸器症状(咳、のどの痛み、鼻水、鼻づまりなど)、頭痛、倦怠感など
潜伏期間
1日~12.5日
予防するためには
感染を予防するためには、手洗い等の手指衛生や、換気等の基本的な感染対策が有効です。
発熱や咳などの症状がある場合
外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。
発熱等でお困りの場合は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
5類移行後の対応・検査キットの種類・外出を控えることが推奨される期間などについては、下記のリンクからご確認ください。
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。主な感染経路は、咳やくしゃみによる飛まつ感染です。発熱などの症状があったら、早めに医療機関で受診しましょう(受診する前に必ず電話で連絡をして、医療機関の指示に従いましょう)。
症状
38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など、全身症状が突然現れます。併せて、普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻水、咳などの症状も見られます。乳幼児では急性脳症を、高齢者や免疫力が低下している人では肺炎を伴うなど、重症になることがあります。
潜伏期間
感染から1日~2日
予防するためには
- 流行前に予防接種を受けましょう。インフルエンザの予防や重症化を防ぐためには予防接種が有効と報告されています(市で実施している高齢者インフルエンザ予防接種は春日部市で受けられる高齢者の予防接種をご覧ください)
- 外出先から帰宅した時、食事の前など、こまめに手を洗いましょう(アルコールによる消毒も効果的です)
- 咳やくしゃみが出るときはティッシュなどで口や鼻を覆う、マスクを着用するなど咳エチケットを心掛けましょう。また、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時は、すぐに手を洗いましょう
- 流行時は、人混みや繁華街への外出を控えましょう
- 室内の適度な加湿や換気を行いましょう
- 規則正しい生活を送り、休養、バランスの取れた食事、適切な水分補給を心掛けましょう
インフルエンザと診断されたら
- 医師の指示に従い、自宅で安静に過ごしましょう
- 目安として、症状が出てから7日間、熱が下がってから2日間は外出を控えましょう
- 家族にうつる場合があるので、家の中でも手洗いやマスクの着用を心掛けましょう
- 定期的に部屋の換気をしましょう
新型インフルエンザの予防対策
人だけでなく、他の動物もインフルエンザウイルスに感染しますが、通常は、人から人へといった同種の間で感染するものです。しかし、ウイルスの性質が変わる(変異する)ことによって、これまでは人に感染しなかったウイルスが他の動物から人に感染するようになり、さらに人から人へ感染するようになります。この変異したインフルエンザウイルスによって起こる疾患が「新型インフルエンザ」で、強毒性のものと弱毒性のものがあります。
新型インフルエンザが発生した場合の市の対策は、春日部市新型インフルエンザ等対策行動計画(PDFファイル:1.2MB)、および春日部市新型インフルエンザ等対策行動計画(概要版)(PDFファイル:305.6KB)をご覧ください。
感染が拡大すると不要な外出ができなくなったり、物流が途絶えたりすることも考えられるので、緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイドを参考に、2週間程度の食料・水・日用品の備蓄を心掛けましょう。
例年冬季に流行するウイルス性疾患です。主な原因ウイルスとして、「ノロウイルス」「ロタウイルス」などがあります。手指や食品などを介して、経口で感染します。健康な人は軽症で回復しますが、子どもや高齢の人は重症化したり、おう吐物を誤って気道に詰まらせることがあるので注意が必要です。
症状
おう吐、吐き気、下痢、腹痛が主な症状ですが、まれに発熱、頭痛、全身倦怠(けんたい)感を伴うことがあります。
潜伏期間
ノロウイルスによる感染性胃腸炎の潜伏期間は通常1日~2日
予防するためには
- 食事前やトイレの後などはせっけんで手指をしっかり洗い、流水で流しましょう
- 加熱調理する料理は、中心部まで十分に火を通しましょう
- 下痢、おう吐などの症状がある場合は、食品を直接取り扱う作業を控えましょう
- おう吐物などを片付ける場合は、マスクや使い捨て手袋などを着用して行い、汚れた場所は塩素系の薬剤で消毒しましょう
RSウイルス感染症は、主に冬季に流行し、乳幼児に多く見られる感染症です。咳やくしゃみ、接触などで感染します。脱水症状や、ゼイゼイするような咳が出て苦しそうな場合は、医療機関を受診しましょう。
症状
鼻水や咳、発熱など 乳幼児は気管支炎や肺炎などを起こしやすいので、呼吸器や心臓に慢性の病気を持つ子どもは注意が必要です。
潜伏期間
1週間程度
予防するためには
- 外出先から帰宅した時、食事前など、小まめに手を洗いましょう
- 感染した場合は、外出を避け、マスクの着用、咳エチケット(咳をするときはハンカチなどで口を押さえる)を心掛けましょう
マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。初秋から冬にやや多く、幼児や小学生の発症が多い病気です。
症状
発熱、長期間続く咳など 一般的に症状が軽いといわれていますが、一部の人は肺炎となり、重症化することもあります。
潜伏期間
2週間~3週間程度
予防するためには
- 外出先から帰宅した時、食事前など、小まめに手を洗いましょう
- 感染した場合は外出を避け、マスク着用、咳エチケット(咳をするときはハンカチなどで口を押さえる)を心掛けましょう
風しんは、咳やくしゃみなどを介して感染する飛沫(ひまつ)感染症です。これまで風しんにかかっていない人、予防接種を受けていない人は注意が必要です。
症状
突然の全身性の発しん、発熱、頚(けい)部リンパ節腫脹(しゅちょう)などが主症状です。基本的に予後は良好ですが、妊娠初期に風しんに感染すると、胎盤を介して胎児に感染し、出生児に白内障、心疾患、難聴などの障害が起こる先天性風しん症候群を発症することがあります。
潜伏期間
感染から14日~21日
予防するためには
- 外出先から帰宅した時など、小まめに手を洗いましょう
- 咳エチケット(咳をするときはハンカチなどで口を押さえる)を守りましょう
- 急な全身性の発しんや発熱などの症状が現れたら、早めに医療機関を受診しましょう
- 受診の際には、マスクを着用する、咳エチケットを守るなど、感染を広げないように注意しましょう
- 定期予防接種(麻しん(はしか)風しん混合予防接種)対象の人は確実に受けましょう
次のホームページでも情報をお知らせしています。
感染症疫学センター(国立感染症研究所のサイト)(外部サイト)
国立感染症研究所「風疹Q&A(2018年改訂版)風疹と先天性風疹症候群について
埼玉県の風しん抗体検査
対象者、実施期間、実施場所などは、埼玉県ホームページ「風しん抗体検査が無料で受けられます」をご覧ください。なお、検査に伴って予防接種を行う場合、市での予防接種費用助成はありません。
風しん抗体検査が無料で受けられます(埼玉県のサイト)(外部サイト)
麻しん(はしか)は、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の感染症です。感染経路は、空気感染、飛沫(ひまつ)感染、接触感染です。感染力が非常に強く、予防接種を受けないと多くの人がかかる病気です。
症状
発熱、咳、鼻汁、発疹を主症状とし、最初の3日~4日間は38度前後の熱が出て、口の中(頬の裏側)に「コプリック斑」と呼ばれる麻しん特有の白いブツブツができます。熱は一時治まりかけますが、再び39度~40度の高熱と全身に赤い発疹が出ます。高熱は3日~4日で解熱し、次第に発疹も消失しますが、しばらく色素沈着が残ります。まれに、肺炎、中耳炎、脳炎を合併することがあるので、注意が必要です。
潜伏期間
感染から10日~12日
予防するためには
手洗い、うがい、マスクなどで感染を防ぐことは難しく、ただ一の予防方法は、予防接種を受けて免疫を獲得しておくことです。
定期予防接種(麻しん(はしか)風しん混合予防接種)対象の人は確実に受けましょう。
麻しん(はしか)・風しん混合予防接種(定期予防接種)対象者
- 1期:1歳~2歳の誕生日の前日までに1回
- 2期:幼稚園、保育所などの年長児に1回
その他、予防接種歴が不明の人は市役所本庁舎2階 健康課 予防担当へお問い合わせください。
ムンプスウイルスに感染して起きる病気です。咳やくしゃみなどを介して感染(飛沫(ひまつ)感染)します。伝染期間は、発病数日前から主要症状が消退するまでです。
症状
耳の下(耳下腺)の腫脹が主症状で、発熱を伴うこともあります。耳下腺の腫れの他に、あごの下(顎下腺)や首のリンパ腺の腫れ、睾丸炎、膵炎、髄膜炎などを合併することがあるので注意が必要です。年長児や成人がかかると合併症の頻度が高くなると言われています。
潜伏期間
2週間~3週間
予防するためには
- 予防接種を受けましょう(おたふくかぜ予防接種は、任意接種で有料です。発症は3歳~6歳が多いため、接種は少なくとも3歳より前に接種することをお勧めします)
- 外出先から帰宅した時など、小まめに手を洗いましょう
- 咳エチケット(咳をするときはハンカチなどで口を押さえる)を守りましょう
手足口病は、ウイルスの感染によって起こる感染症で、乳幼児を中心に、主に夏に流行します。
症状
口の中の痛みや、口腔(こうくう)粘膜、手のひら、足の裏などに水泡性の発疹が現れます。
- 発疹が手足全体、ひじやひざ、あるいはおしり周辺に多数現れることもあります
- 軽い発熱と食欲不振・気分不快、のどの痛みを伴うこともあります
- 重症になることは少なく、多くの場合7日~10日で治ります
- まれに、髄膜炎などを伴うことがあります
- 高熱や頭痛、おう吐がひどい場合などには、早めに医師の診察を受けましょう
潜伏期間
3日~5日
予防するためには
手をよく洗うことが大切です。
- 患者の便には1カ月ほど病原体のウイルスが出ている可能性があるので、特に手足口病にかかった子どものおむつを替えた後などは、よく手を洗いましょう
- おしりを拭いた時などにウイルスが付着する可能性があるので、患者に使用するタオルは別に用意しましょう
伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)はりんご病とも呼ばれ、感染は10歳未満の子どもに多くみられます。患者の咳やくしゃみなどに含まれるウイルスを吸い込むこと(飛沫感染)や、ウイルスが付いた手で口や鼻などに触れること(接触感染)で感染します。感染しないよう注意し、体調の悪いときは早めに医療機関を受診しましょう。
症状
10日~20日の潜伏期間の後、両頬に境界鮮明な紅い発疹がみられます。頬の発疹に続いて、手・足に網目状の発疹がみられますが、これらは1週間前後で消失することがほとんどです。頬に発疹が現れる7日~10日くらい前に微熱や風邪のような症状がみられ、この時期にウイルスが最も多く排泄されます。妊娠中に感染した場合、まれに胎児の異常(胎児水腫)や流産が生じる可能性があります。
潜伏期間
10日~20日程度
予防するためには
- 外出先から帰宅した時、食事前など、小まめに手を洗いましょう
- 咳やくしゃみが出るときはティッシュなどで口を覆う、マスクを着用するなど咳エチケットを心掛けましょう
- 妊娠中あるいは妊娠の可能性がある女性は、できる限り患者に接触しないようにする、手洗い、マスクをするなどして注意しましょう
ヘルパンギーナは発熱や口の中に水疱ができるウイルス性の咽頭炎で、乳幼児を中心に夏季に流行します。 患者の咳やくしゃみなどのしぶき(飛沫)に含まれるウイルスを吸い込むこと(飛沫感染)や、ウイルスが付いた手で口や鼻などの粘膜に触れること(接触感染)、便の中に排泄されたウイルスが口に入ること(経口感染)で感染します。有効な予防接種や特別な治療法はありません。
症状
- 38~40度の発熱で発症し、同時にのどが痛む病気で、発熱が1~3日続き、食欲不振、全身のだるさ、頭痛などを起こします
- 咽頭痛で食事が摂れないことがあり、脱水症になることがあります
- 稀に無菌性髄膜炎や心筋炎を併発することもありますので注意してください
予防するためには
- こまめに手を洗いましょう
- 患者との密接な接触をできるだけ避けましょう
- 集団生活ではタオルの共用を避けましょう
- 特に患者が乳幼児の場合には、おむつ交換後の手洗いを徹底しましょう
咽頭結膜熱は、夏にプールの水を介して流行することが多く、プール熱とも呼ばれていますが、冬でも流行することがあります。 主に咳やくしゃみによる飛沫感染をします。また、プールでの接触やタオルを共有することでも感染することがあります。
症状
アデノウイルス感染による発熱(38~39度)、のどの痛み、結膜炎が主な症状です。
潜伏期間
潜伏期間は5~7日といわれています。
予防するためには
- マスクの着用等普段からの咳エチケット(咳やくしゃみの際は、ハンカチやマスクなどで口・鼻を覆う)を心掛けましょう。
- 外出先から帰宅した時、食事の前など、こまめに手を洗いましょう。また、むやみに目や口にふれたり、こすったりしないようにしましょう。
- 家族や周囲の人がかかってしまったときは、密接な接触を避け、タオルの共用はしないようにしましょう。
- 規則正しい生活を送り、休養、バランスの取れた食事を心掛けましょう。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは、血清型がA群のレンサ球菌による上気道感染症です。レンサ球菌は、細菌性急性咽頭炎の最も一般的な原因菌で、学童期の小児に多く見られます。まれに重症化し、のどや舌、全身に発赤が広がる「猩紅熱(しょうこうねつ)」に移行することがあります。また、リウマチ熱や腎炎の原因となる場合もあります。
症状
2~5日間の潜伏期間の後、突然38度以上の発熱、のどの痛み、苺状の舌などの症状が現れます。
予防するためには
- マスクの着用等普段からの咳エチケット(咳やくしゃみの際は、ハンカチやマスクなどで口・鼻を覆う)を心掛けましょう。
- 外出先から帰宅した時、食事の前など、こまめに手を洗いましょう。また、むやみに目や口にふれたり、こすったりしないようにしましょう。
- 家族や周囲の人がかかってしまったときは、密接な接触を避けるようにしましょう。
- 規則正しい生活を送り、休養、バランスの取れた食事を心掛けましょう。
発熱や体調不良の時には
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、適切な抗菌薬治療を開始すれば24時間以内に感染力はなくなるとされています。早めに医療機関を受診し、早い回復につなげましょう。
- 安静にして休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- 水分を十分に補給しましょう。
- 同居人のいる方は、家庭内でもマスクをするようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 予防担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
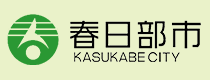

更新日:2024年06月14日