「建築協定」で魅力的な街づくり

建物を建築するときは、都市計画法や建築基準法などで用途・規模・高さなどの規制がありますが、法は全国一律であり、国が総括的に定めた最低限の基準です。また、市では「埼玉県建築基準法施行条例」「春日部市開発事業の手続き及び基準に関する条例」などで、一定の条件に該当する建築物や開発行為の規制を行っていますが、地域ごとにさまざまな事情がある中、公平な規制を課す「条例」では、地域住民のニーズに合った街づくりは困難な状況です。
そこで、市では、各地域でそこに暮らす住民・関係者などが自らルールを作り、「魅力的な街づくり」を行うための一つのツールとして、「建築協定」を推奨しています。
建築協定とは
各地域でそこに暮らす住民・関係者などがその全員の合意のもとに、建築物などに関するルールを作り、お互いにこのルールに従うことを約束する制度です。一度作ったルールは、協定が有効な期間内は土地の所有者が替わっても新たな所有者に引き継がれるため、安定的に「魅力的な街づくり」が保持されます。また、当初合意が得られなかった土地でも、「建築協定区域隣接地」に設定することにより、合意が得られたときにいつでも協定区域に加えることができます。
建築協定を行うには2つの手法があります
- 既成市街地における建築協定…協定に合意した住民の一団の土地で行う手法
- 宅地分譲に伴う建築協定…開発行為を行う一団の土地において事業者が設定する手法
建築協定で定めるルール
- 建築協定の区域
- 建築物に関する基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、意匠、外構、緑化など)
- 建築協定の有効期間
- 建築協定に違反があった場合の措置
建築協定で行う環境整備の例
- 住宅街で行う住環境整備
- 商業地域としての町並み形成
- 工業地域における美観形成
建築協定のメリット
現在地域が抱えている問題または将来起こり得る問題の回避に役立ちます
- 住宅街に店舗など集客施設が建築計画される…建築用途のルール作り
- マンションや高層の建築物が建築計画される…高さ制限のルール作り
- 敷地が細分化される計画がされる(通風などの悪化)…敷地面積規模のルール作り
住宅地の美観形成、緑化の推進に役立ちます
- ブロック塀を規制する
- 生け垣の奨励を規定する
- 建物の屋根・外壁の色彩・形を統一するよう規定する
沿道の緑化
市では、道路沿いに植樹されている生垣のうち、所定の条件に合うものについて、維持管理に要する費用の助成を行っています。建築協定と併せて緑化の推進にご利用ください。なお、助成金に関しては、市役所4階 公園緑地課へお問い合わせください。
建築協定の手続きの進め方
事前相談
お住まいの地域で、または新たに宅地分譲をしようとする場合に、住環境の改善・維持のために建築物に関するルールを決めたいと考えたら、市役所4階 建築課へ相談してください。
建築協定認可申請
建築協定で定める事項がまとまり、関係権利者の同意が得られたら、申請書類を作成し、建築課へ提出してください。
縦覧
建築協定書の提出があった旨を公告し、縦覧します。
- 縦覧場所…市役所4階 建築課窓口
- 縦覧期間…21日間以上
公聴会
縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行います。
認可
市長が建築協定を認可、公告します。
協定者の代表者は、協定書の写しを協定者に配布し、運営委員会を設立してください。
縦覧
認可した建築協定書を縦覧します。
縦覧場所…市役所4階 建築課窓口
申請書類
建築協定認可
- 建築協定認可(変更認可・廃止認可)申請書(Wordファイル:24.3KB)
- 建築協定認可(変更認可・廃止認可)通知書(Wordファイル:23.6KB)
- 建築協定書
- 建築協定区域および協定区域内の地形地物を表示する図面
- 付近見取り図
- 建築協定区域隣接地を定める場合は建築協定区域隣接地の区域協定区域隣接地内の地形および地物を表示する図面
- 区画面積表
- 建築協定同意書
- 土地の所有者などの調書
その他(建築協定認可以外)
一人建築協定が効力を有することとなった旨の届出書 (Wordファイル: 20.8KB)
パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築安全担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム
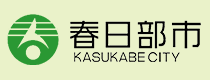

更新日:2026年02月10日