10月27日 地域の田んぼを活用して赤米の稲刈り体験が行われました
令和7年10月27日、赤沼農水里環理組合と藤塚小学校が連携して赤米の稲刈り体験が行われ、5年生2クラスが参加しました。この活動は多面的機能支払交付金を活用し、農地や水路などの地域資源が持つ教育の場としての機能増進を図っています。
昨年までは地元農家の筒野さんが、赤米作りを広げていくために自主的に藤塚小学校と豊野小学校との田植え・稲刈り体験を行っていました。今年から地域でこの取り組みを守っていこうと、筒野さんがメンバーの一員となっている多面的機能支払交付金の活動組織「赤沼農水里環理組合」の活動に位置づけました。
多面的機能支払交付金…農業・農村の有する多面的機能(洪水や土砂崩れなどの防止、環境保全、美しい風景の形成など)の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援しています
稲刈り体験の様子


はじめに、筒野さんから稲刈りと稲架掛け(はさがけ)のやり方について説明がありました。5月の田植え体験の際に稲の言葉の意味を教わったこどもたちは、筒野さんから「稲の言葉の意味はなんだっけ?」と聞かれると、元気いっぱい「命の根っこ!」と声を揃えて答えていました。
いねのいは命のい。いねのねは根っこのね。稲という言葉は命の根が語源といわれており、こどもたちは命をつなぐ大切なものを植えて、収穫して、食べる体験をしています。

筒野さんによるお手本

刈る人、束ねる人で分担

ザクザク刈り進めます

揃えた稲を縛ります

束ねた稲を二等分にして交差

いざ、実践!

慣れてきてスピードアップ

稲架掛けした赤米の稲穂
約1時間半で稲刈り体験は終了。田んぼには、稲架掛けした赤米の稲穂がずらり。日本の秋の原風景がそこにはありました。稲架掛けで乾燥した後は脱穀し、残ったワラはしめ縄にして赤沼香取神社に奉納するそうです。農作業と五穀豊穣を願う習わしは深く結びついているのですね。
今回収穫した赤米は熟成させ、来年の給食に登場する予定です。おいしいお米が今から楽しみですね。
地元で採れる新鮮で安全・安心な農産物を給食へ
筒野さんは学校給食に使用する野菜・果物の提供生産者に登録しており、この事業を通じて給食に赤米を提供しています。
学校給食課では、提供生産者の登録を受け付けています。詳しくは学校給食への野菜・果物の提供生産者を募集しますをご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課 農地担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
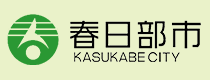

更新日:2025年11月26日