医療費の助成・重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、障がいのある人が病院などで診療を受けた場合、保険診療における最終的な医療費本人負担額を助成します。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
受給者証の更新について
所得審査を行うため、毎年10月1日に受給者証の更新を行います。所得審査に伴う受給者証の更新は自動で行われるため、お手続きは不要です。
新しい受給者証は、毎年9月下旬までにお送りします。
(注意)手帳の更新などの理由から、お手続きが必要な場合もありますので、下記〈自動更新の対象とならない方〉をご確認ください。
自動更新の対象とならない方
・身体障害者手帳および療育手帳の再認定月が9月以前の方
・精神障害者保健福祉手帳の有効期限が9月30日以前の方
新たな手帳が交付された際に更新手続きの案内が行われますので、更新のお手続きをお忘れないようお願いいたします。
対象者
原則、市内に住所を有し、健康保険に加入している人で、障害要件に該当する人。
ただし、65歳以上で新たに重度心身障がい者となった人は対象外です。
障害要件(重度心身障がい者となる要件)
- 身体障害者手帳1級~3級
- 療育手帳マルA、A、B
- 精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床への入院費用は助成されません)
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人(身体障害者手帳4級の一部、精神障害者保健福祉手帳2級、障害年金1級および2級など)
所得制限
本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が限度額を超える場合は、障害要件を満たしていても医療費助成を受けられません。
|
扶養親族の数 |
所得制限限度額 |
給与収入換算額(注釈) |
|---|---|---|
|
0人 |
3,661,000円 |
5,252,000円 |
|
1人 |
4,041,000円 |
5,728,000円 |
|
2人 |
4,421,000円 |
6,203,000円 |
|
3人 |
4,801,000円 |
6,668,000円 |
(注釈)給与収入換算額は、目安です
- 所得の合計額から各種控除額を差し引いた額が所得制限限度額以下であれば、医療費助成を受けられます
- 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します
- 当該扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族の場合は、1人につき所得制限限度額に10万円を加算します
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき、所得制限限度額に25万円を加算します
- 障害年金、遺族年金などの非課税年金は所得に含まれません
審査フロー図及び資格取得時期ごとの所得審査に使用する課税年度について (PDFファイル: 75.7KB)
注意事項
所得が限度額を超えた場合は、次のとおり一定期間、医療費助成を受けられません。
- 1月~9月に新規申請した場合…その年の9月30日まで支給停止
- 10月~12月に新規申請した場合…翌年の9月30日まで支給停止
毎年、10月の更新時に所得審査を行います。
所得の範囲
所得制限の対象となる所得の範囲は、以下の通りです(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定に準じます)。
- 総所得金額(注意)
- 退職所得(退職によって受けられる年金の一時金など。いわゆる「退職金」とは異なる。)
- 山林所得
- 土地の譲渡などにかかる事業所得
- 長期・短期譲渡所得金額
- 先物取引にかかる雑所得
- 条約適用利子および条約適用配当金など
(注意)総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(4を除く)、給与所得、譲渡所得(5を除く)、雑所得(課税対象年金など)、一時所得です。また、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額となります。
控除項目
|
控除名 |
控除額 |
備考 |
|---|---|---|
|
雑損控除 |
当該控除の実額を控除します |
納税者自身あるいは生計を一にする扶養親族などの所有する日常生活上必要な住居や家財が災害や盗難などにより損害を受けた場合に受けられる控除 |
|
医療費控除 |
当該控除の実額を控除します |
納税者自身あるいは生計を一にする扶養親族などのために納税者が1年間に一定の金額以上の医療費を支払ったときは200万円を限度に控除を受けることができる |
|
社会保険料相当額 |
一律8万円 |
社会保険料は控除できない(社会保険料控除相当額として一律8万円が控除できる) |
|
小規模企業共済掛金控除 |
当該控除の実額を控除します |
小規模共済組合法の規定する第1種共済契約に基づく掛金や、条例に基づく扶養共済制度の掛金などを支払った場合に適用がある |
|
障害者控除(本人) |
27万円 |
障害者控除を受けている場合 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病手帳所持者など) |
|
特別障害者控除 |
40万円 |
特別障害者控除を受けている場合 (身体障害者手帳1~2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級など) |
|
障害者控除 (同一生計配偶者・扶養親族) |
一人につき27万円 |
同一生計配偶者、扶養親族が障害者控除を受けている場合 |
|
特別障害者控除 (同一生計配偶者・扶養親族) |
一人につき40万円 |
同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者控除を受けている場合 |
|
寡婦控除 |
27万円 |
夫と死別、または離婚した後に再婚していない者などで、扶養親族があり、自身の所得が500万円以下の場合(ひとり親控除に該当しない場合のみ) |
|
ひとり親控除 |
35万円 |
生計を同じくする子があり、自身の所得が500万円以下の単身者 |
|
勤労学生控除 |
27万円 |
高校、大学、または一定の専修学校・各種学校の生徒で、自ら働いて得た給与所得や雑所得がある者(年間所得75万円以下) |
|
配偶者特別控除 |
当該控除の実額を控除します |
納税者自身と生計を一にする配偶者との、それぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除 |
- 控除できるのは、市・県民税の課税台帳上実際に控除されたもののみです
- 控除する所得額は、課税対象となる全ての所得からであり、課税台帳上の課税標準額(各種控除を控除した後の額)からさらに控除できるとしたものではありません
- 各種控除は、地方税法による市・県民税の課税台帳上実際に控除されたものでなくてはなりませんが、一部を除き、控除する額は所得税法にしたがった額となりますので注意してください
- 分離課税の所得がある場合、分離課税分の課税所得を出して、課税所得を合計した上で控除していきます
助成対象
医療保険の適用される自己負担金額から健康保険組合から支給される高額療養費・付加給付金を除いた最終的な医療費本人負担額を助成します。
助成の対象になるもの
- 医療保険が適用される最終的な医療費・薬剤費
- 治療用装具(医師が必要と認めた補装具の場合、健康保険の療養給付後の一部負担金を助成します)
助成の対象にならないもの
- 医療保険の適用されないもの(差額ベッド代・健康診断・予防接種など)
- 入院時の食事代
- 介護保険の利用により支払ったもの
- 診断書などの文書料
- 幼稚園または保育所、学校でケガなどをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの
- 健康保険組合から支給される高額療養費・付加給付金
- 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)など他の公費負担医療制度の対象となるもの(自己負担額は助成対象です)
- 仕事上のけがや病気など労災保険が適用されるもの・労働基準法に従い雇い主負担のもの
- 交通事故やケンカによるケガなどの第三者行為の対象となるもの
お願い
- 今後も制度を安定的に運営するため、ジェネリック医薬品の活用をお願いします
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします
- 収入がなかった方も毎年度、市・県民税の申告をお願いします。未申告の場合、高額療養費の限度額が高くなるなど過分な自己負担が生じる場合があります。
- 入院等で高額な患者負担額が生じる場合は、あらかじめ限度額適用認定証等の取得をお願いします。
登録方法
次のものを持って、市役所2階 障がい者支援課または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当で受給資格登録の手続きをしてください。
- 重度心身障害者医療費受給資格登録申請書
- 高額療養費の確認等に関する同意書
- 障害者手帳
- 健康保険情報が分かるもの (資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルから資格情報をダウンロードしたもの)
- 振込口座が分かるもの(原則、本人名義の金融機関口座)
- 個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)
助成方法
「春日部市重度心身障害者医療費受給者証(以下受給者証)」は、埼玉県内の医療機関等で利用できます。ただし、医療機関等によっては、受給者証を提示しても窓口払いが必要な場合があります。
あん摩マッサージ、はり・きゅう師、柔道整復師の施術所等は春日部市と協定を締結した市内の施術所等のみが窓口払いなしとなります。
助成方法は、次のいずれかです。なお、自立支援医療(更生医療・精神通院医療)などの他の公費負担医療制度が利用できる場合は、そちらが優先されます。
1.県内の医療機関等を受診した場合(窓口払いなし)
受給者証を、マイナ保険証(保険証の利用登録が済んでいるマイナンバーカード)・資格確認書・保険証のいずれかや特定疾病療養受療証等とあわせて医療機関等窓口へ受診ごとに受給者証を提示してください。医療費一部負担金の支払いが不要となります。
- 医療保険制度が適用されないものは支払いが必要です。
- 受給者証を提示しない場合は、医療費窓口払いが生じる場合があります。
- 医療機関等によっては、受給者証を提示しても窓口払いが生じる可能性があります。その場合は、次の「2.県外の医療機関等を受診した場合(償還払い)」の方法で助成を受けてください。
- 人工透析などの特定疾病で院外処方が発生する場合、加入する健康保険によって、県内医療機関であっても病院と薬局とで助成方法が異なります
|
特定疾病の受診で院外処方 が発生する場合 |
後期高齢者医療広域連合加入者 春日部市国民健康保険加入者 |
左記以外の健康保険加入者 |
|---|---|---|
| 人工透析などを受けた病院(県内) | 窓口払いなし | 窓口払いなし |
|
上記病院の処方せんにより、 薬を処方された薬局(県内) |
窓口払いなし | 償還払い(窓口払いあり) |
2.県外の医療機関等を受診した場合(償還払い)
県外の医療機関等、春日部市と協定を締結した市内施術所等以外の施術所等を受診した場合は、医療費一部負担金を支払い、重度心身障害者医療費請求書に医療機関等が発行する領収書等を添えて、市役所2階 障がい者支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当または武里出張所へ提出してください。
- 医療保険制度が適用されないものは助成対象外です。
- 月ごと・医療機関等ごと・入通院ごとで医療費請求書を作成してください。なお、1つの医療機関等で歯科を含む複数の診療科を受診した場合は、歯科診療分として医療費請求書をもう1枚作成してください
- 医療費の請求は受診された月の翌月以降に、ひと月分をまとめてご提出ください。ひと月の医療費は末日で算定するため、月途中での請求はご遠慮ください。
- 数か月に一度など定期的な請求をお願いします。
助成時期・時効
- 原則、請求した月の約3カ月後の15日(休日に当たる場合は、その直前日)に、申請した金融機関口座に振り込みます(高額療養費や付加給付金に該当する可能性がある場合は、支給状況が確認できるまで保留となります)
- 医療費請求の期間は、医療費を支払った日の翌日から起算して5年以内となります。それを過ぎたものは時効により助成できません。
- 高額療養費の請求時効は2年となります。
他の医療制度
各制度の詳細について下記リンク先をご参照ください。
埼玉県ホームページ’(福祉3医療費支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について)
再交付・変更・喪失などの手続き
次の場合は、市役所2階 障がい者支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当で手続きをお願いします。
重度心身障害者受給者証を紛失・破損した場合
障害者手帳を持って、再交付の手続きをしてください。
住所・医療保険(記号番号の変更含む)・振込口座など登録内容に変更がある場合
障害者手帳、変更内容の分かるもの、重度心身障害者医療費受給者証(支給停止中の人を除く)を持って、変更の手続きをしてください。
市外への転出・お亡くなり・障害要件が非該当・生活保護を受給するようになった場合
受給資格が無くなりますので、喪失の手続きをしてください。また、重度心身障害者医療費受給者証を返却してください(支給停止中の人を除く)。受給資格喪失後に受給者証を使用して受診した場合は、その医療費を返還してもらいます。
なお、障害要件が非該当になった場合の受給資格喪失日は以下のとおりです。
身体障害者手帳・療育手帳
再認定により障害程度が非該当になった場合
障害程度が障害要件非該当となった手帳交付日の前日または再認定年月の月末
- 再認定の年月の末日より前に非該当となる手帳が交付された場合
例:障害程度が有効な手帳の有効期限が5月31日で4月8日に再認定の手帳が交付された場合は4月7日まで有効
- 再認定の時期を過ぎて非該当となる手帳が交付された場合
例:障害程度が有効な手帳の有効期限が5月31日で6月8日に再認定の手帳が交付された場合は5月31日まで有効
精神障害者保健福祉手帳
手帳の更新により障害程度が非該当になった場合
更新前の手帳の有効期限の日
申請書などダウンロード
1.重度心身障害者医療費受給資格登録申請書
重度心身障害者医療費受給資格登録申請書 様式 (Wordファイル: 17.9KB)
重度心身障害者医療費受給資格登録申請書 様式 (PDFファイル: 102.4KB)
重度心身障害者医療費受給資格登録申請書 記入例 (PDFファイル: 158.4KB)
保険情報にかかる添付書類(社会保険加入の方のみ) (PDFファイル: 1.1MB)
2.高額療養費の確認等に関する同意書
高額療養費の確認等に関する同意書 様式 (Wordファイル: 12.4KB)
高額療養費の確認等に関する同意書 様式 (PDFファイル: 75.3KB)
高額療養費の確認等に関する同意書 記入例 (PDFファイル: 161.1KB)
3.重度心身障害者医療費請求書(受給者用)
1.受給者が75歳未満の場合
重度心身障害者医療費請求書(受給者用・70歳未満)様式 (Wordファイル: 21.0KB)
重度心身障害者医療費請求書(受給者用・70歳未満)様式 (PDFファイル: 165.9KB)
2.受給者が75歳以上の場合
重度心身障害者医療費請求書(受給者用・75歳以上)様式 (Wordファイル: 23.6KB)
重度心身障害者医療費請求書(受給者用・75歳以上)様式 (PDFファイル: 201.6KB)
3.記入例(共通)
重度心身障害者医療費請求書(受給者用)記入例 (PDFファイル: 473.7KB)
4.重度心身障害者医療費請求書(市と協定を結んだ市内の接骨院、鍼灸 (しんきゅう)院など用)
重度心身障害者医療費請求書(市と協定を結んだ市内の接骨院、鍼灸 (しんきゅう)院など用) 様式 (Wordファイル: 25.0KB)
重度心身障害者医療費請求書(市と協定を結んだ市内の接骨院、鍼灸 (しんきゅう)院など用) 様式 (PDFファイル: 164.0KB)
重度心身障害者医療費請求書(市と協定を結んだ市内の接骨院、鍼灸 (しんきゅう)院など用)記入例 (PDFファイル: 344.8KB)
5.重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書 様式 (Wordファイル: 23.9KB)
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書 様式 (PDFファイル: 72.7KB)
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書 記入例 (PDFファイル: 122.5KB)
6.重度心身障害者医療費資格内容変更・喪失届
重度心身障害者医療費資格内容変更・喪失届様式 (Wordファイル: 16.9KB)
重度心身障害者医療費資格内容変更・喪失届様式 (PDFファイル: 97.5KB)
重度心身障害者医療費資格内容変更・喪失届 記入例 (PDFファイル: 187.0KB)
保険情報変更にかかる添付書類(社会保険加入の方のみ) (PDFファイル: 1.1MB)
7.所得状況届
お問い合わせ
障がい者支援課 障がい者医療担当
- 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
- 電話:048-736-1131
- ファックス:048-733-0220
庄和総合支所 福祉・健康保険担当
- 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
- 電話:048-746-9702
- ファックス:048-746-4797
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
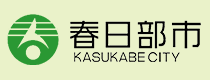

更新日:2025年12月16日